�X�|���T�[�����N
�M�����O�f��̋�����
���̐��ɐ�����l�X�̎�����10�i�K�ɕ�����ƁA�g�b�v10%�̍��v�����͂��̑�90%�̍��v������荂���A����Șb�����݉��ł������Ō��C���e���C�������܂ɖڂɂ���B
�����ɂ͂���ȃC���e���C�����C���e�����C���ꂽ����A�ׂ̑�ň���ł�����X�̑O��ʂ�߂��čs����OL���������ے����F�����d�ԂɂԂ����܂��B
�����Ă���Ȗ����ԗ��̑S�����̎�������l�ʼn҂��グ����͂ǂ����̍����z�e���ł܂��V���N�ɂ���܂�Ė����Ă���B
����ȕn�x�̍��̘b�Ȃ�ĕ����O���邭�炢��������āA�������тɖ����ɕ��������Ėl��͗����オ��Ȃ���ƕ������B
���������̏u�Ԃɉ�ɋA�肷���ɂ܂��Ȃɒ����B
�����オ��Ɩl��͋C�Â��A���������܂�ɂ��ۍ��Ȏ��ɁB
�������n�߂鎑�{���Ȃ���A�������n�߂�m�b���Ȃ����X�L�����Ȃ��B�����Ȃ�ƈ�ԕK�v�ȓx����E�C�͕��������Ă��Ȃ��B
���̒��̓����͂������đ�l�����Ȃɂ����l�X��D�����}���Ă����B
�����ȍK����͂߂Ηǂ�����Ȃ����A�����Ȉ����������������Ȃ����B
�x�O�̒�t���ꌬ�ƁA�t�@�~���[�J�[�A�q���Ƃ̋x���̂��o�����A����Ȑl�������Ĉ����Ȃ��B
�^�ʖڂɃR�c�R�c������A�Εׂ͔����A�Ƒ��̈������������厖�B
�g���Â��ꂽ�����ς͖����ɕς���Ă��Ȃ��B
�f��̒��ł�����ȓ����ς��Ƒ�����N���C�}�b�N�X�̗ܗU���W�J��ʂ��Č���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��B
����ȉf��ɔ�ׂ�Ɓu�X�J�[�t�F�C�X�v�Ƃ����f��͑S�������ē����I�Ƃ͌����Ȃ����낤�B
�Ȃ��Ȃ��l���́A��ɗ��l�Ԃ��E���A��Ȃ�����n��A�R�J�C�����ʂɎJ���ĉ������҂ɂȂ�B
�n�C���X�N�n�C���^�[���̐����l���������̉f��̔������A�����I�����l��`���f�悩��ł������f��ƌ����Ă��ǂ����낤�B
����ljf��̕\�w���������Ă��̍���ɗ������̂�����̂͂��������Ȃ��B
���݂ǂ�ŁA��܂݂�ŁA���肩��N�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��j��`�������̉f��ɂ͂����̋���ȓ����ς��\������Ă���B
�f��̍���ɗ����{������������邱�Ƃ����f��ӏ܂̑�햡���B
�u�X�J�[�t�F�C�X�v��1983�N�̃A�����J�̃M�����O�f��B
�ē̓u���C�A���E�f�E�p���}�A�r�{�̓I�����@�[�E�X�g�[���A�o���̓A���E�p�`�[�m�A�X�e�B�[�u���E�o�E�A�[�A�~�V�F���E�t�@�C�t�@�[�ȂǁB
�ē̃u���C�A���E�f�E�p���}�̓X�e�B�[�u���E�L���O����́u�L�����[�v�Ńq�b�g���������̂̂��̌�͂Ȃ��Ȃ��ǂ���i����ꂸ�Ƃ����������Ă����B
����r�{�̃I���o�[�E�X�g�[���͌�Ɂu�v���g�[���v�u�E�H�[���X�v�ȂǎЉ�h�f��̖���ƂȂ邪���̎��͊ē����f�悪�厸�s�ɏI����Ă����B
����ȓ�l���^�b�O��g�̂����́u�X�J�[�t�F�C�X�v���B
���ۂ�1932�N���J�̃n���[�h�E�z�[�N�X�ē�u�Í��X�̊���v�����C�N�Ȃ̂ŃI���o�[�E�X�g�[���̋r�F�Ƃ����̂���������������Ȃ��B
�֎�@����ɈÖ����݂̃M�����O�A�A���E�J�|�l�����f���ɂ����u�Í��X�̊���v��1980�N���ɕς��A���̖������h���b�O�̖����ɕϊ����A�i���ӎ���ǓƊ���}�������I���o�[�E�X�g�[���̋r�{�A������ߏ�ȃo�C�I�����X�`�ʂ������ĕ`���ꋉ�̃G���^�e�C�������g�f��Ɏd���ďグ���f�E�p���}�̉��o�͂͌������B
�s���̎����̓�l�̟T���������荇���Ĕ���������i�Ƃ�������B
�s���̓�l�Ɠ����悤�ɁA���̉f��̎�l���g�j�[�E�����^�i(�A���E�p�`�[�m)���܂������s���̐l�Ԃ��B
�����^�i�̓L���[�o�ɐ��܂�A�{�[�g�s�[�v��(�����╴���n���狙�D��b�g�Ȃǂœ�Ƃ��ē����l�X)�Ƃ��ăA�����J�ɓn���Ă����B
���J�X�g����`�҂Ŕƍߎ҂ł������g�j�[�͗F�l�̃}�j�[(�X�e�B�[�u���E�o�E�A�[)�Ƌ��ɓ�̊u���{�݂ɓ�����A�����ň˗����ꂽ�E�l�ƈ��������ɃO���[���J�[�h(�A�����J���O���i�Z��)����ɂ���B
�댯�ȃ��X�N��Ƃ����ɂ�������炸�g�j�[�ɉ���Ă���d���͔ƍ߂��Ȃ��d���̂݁A���̓��ł��n�����҂݂̂��댯��Ƃ��A��ɗ����̂����̗��v�����������\���͕ς��Ȃ��B
���̕s���̏���g�j�[�Ƃ����j���ǂ�����Ĕ����o���A�ǂ�����Ĉ��̓��̒��_�ɓo���Ă��������u�X�J�[�t�F�C�X�v�Ō���镨�ꂾ�B
�`���Łu�X�J�[�t�F�C�X�v�ɋ���ȓ����ς��\������Ă���ƋL�������R�̓g�j�[�E�����^�i�̐��������q�ׂɒ��߂Ă���Ε�����B
�A���E�p�`�[�m��������g�j�[�E�����^�i�Ƃ����j�͏u���ԂɈ��̓��̃g�b�v�ւƏ��l�߂Ă����킯�����A�ނɂ͓��ʂȕ��킪����킯�ł͂Ȃ��B
�܂��A�����^�i�̓`�r�łЂ��������j���A�ؓ����Ȃ��A�����������悤�ɂ����݂��o�Ȃ��B
���}���L�̓��̃L���A�����X�g���[�g���C�Y�������Ă���킯�ł��Ȃ��A�������n�����Ă��������Ȃ��፷���ő�����ɂݕt���邱�Ƃ����ł��Ȃ��B
����Ƃ������l�����Ȃ��A�l�]�͂��邪�F�����L���[�o����̗���҂ŃS���c�L���肾�B
�������g�j�[�͒N�ɂ������Ȃ��s���̖�S���������B�ǂ�ȑ啨�ɂ��������Ȃ��K�b�c�������g�j�[�̗B�ꎝ���Ă��镐�킾�B
���肪�ǂ�Ȃɋ��������Ă��悤�ƁA�ǂ�Ȃɗ͂������낤�ƁA�ǂ�ȋ������������悤�ƃg�j�[�Ƃ����j�͋����Ȃ��B
���Ԃ��ڂ̑O�Ń`�F�[���\�[�Ŏ葫��藎�Ƃ���悤������̊ዅ���Ă��s���������ɔ��R�I�Ȋ፷��������������B
�r�͂��m�b���Ȃ��g�j�[���A�ނ̕����Ȃ��A�����Ȃ��A�܂�Ȃ��A���̐M���ɂ͂���Ƃ����������͂Ȃ��B
�u���̕���̓K�b�c�ƐM�p�v
�������悤�Ƀg�j�[�ɂ���̂̓K�b�c�������B
�g�j�[�͕����ʂ�K�b�c�݂̂ŐM�p���������A���̓��̒��_�ւƏ��l�߂�B
�R�c�R�c�n���ɁA�Εׂ͔����A�����ȍK���A�����Ȉ��B
�����̓����������ĊԈ���Ă͂��Ȃ��A�����������͑��ʓI�ɑ����邱�Ƃ��d�v���B
�����̓����͊m���ɊQ��������A�i�����������Ă������邩������Ȃ��B
�i���Ɍ������Đ����ɋ��ڂ��Ƃ��鎞�A�����オ���Ď��������̗͂Ő����Ă������Ƃ��鎞�A�����̐l�͍��܂���B
�F�䖝���Đ����Ă���A�������c
�Y���Ă����C�ɏ]���A�������c
�����������ÂR�c�R�c�Ɛςݏグ�Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��A�������c
�S���܂ꂻ���Ȏ��A�����ɂ��ł��炵�������̊Â����t���A��l�̐l�Ԃ̂����ۂ��������F�����Ă��܂��B�����Ĉ�l�̐l�Ԃ͎����ɉ��̕�����Ȃ����ƂɋC�Â������B
�m�b�̂Ȃ��A�Z�p�̂Ȃ����C�Â������B
���������������N������Ȃ�Ď����Ă���̂��낤���B
���痧���オ���Ĉ���ݏo���ɂ̓g�j�[�̂悤�ɃK�b�c�����ŏ\�����B
�����Ɖ�������̕ǂ������������͂�����B�����������ƃK�b�c�ŏ����B�������玟��ɐM�p�����Ă���B
�m�b��Z�p�͂��̂܂ɂ��g�ɂ��Ă���B
�L���[�o����卑�A�����J�ɗ��ꒅ�����A�`�r�łЂ���������l�̒j���K�b�c�����Ńg�b�v�܂ŏ��l�߂鐶���l�́A���̐��E�ŗ͋��������Ă����l�Ԃ̂��߂̒������I�Ȑ����l�Ƃ�������B
�u�X�J�[�t�F�C�X�v�̃o�C�I�����X�ȕ\�ʂł͂Ȃ��A�g�j�[�Ƃ����j�̐����l���������茩�����邱�Ƃɂ��̉f��̐^�̉��l������ƌl�I�ɂ͎v����B
��i�̒��ՂŁA���̓��̃g�b�v�ɏ��l�߂��g�j�[���������X�g�����ōȂ̃G�����B���i�~�V�F���E�t�@�C�t�@�[�j�ƌ��_����V�[��������B
�G�����B���͗��܂肩�˂ă��X�g���������яo���A��l�c�����g�j�[�͍������X�g�����ŐH������������B������₩�ȖڂŌ�����B
�g�j�[�͋������B�Ɉ��Ԃ���
�u�������Ă��H�����������B���O��͉����w�����āu�����͈��}���v�ƌ����B���Ⴀ���O��͉����H�P�l���H���O��͕��C�ʼnR�����B�ł����͐^����������Ȃ��B���݂����Ȉ��}�͂������ڂɂ�����Ȃ����B�����A���}�ɂ��₷�݂�������v
�����Ō����R�́A��l�̐l�Ԃ������オ�����Ƃ��ɓ��ɎC�荞�܂ꂽ���̂悤�ɑz�N������ʓI�ȓ����ςƂ�������B
�����ȍK���ŗǂ�����Ȃ����B
�R�c�R�c�w�͂��Ă�����������Ȃ����B
���E���̊F���A��/���Ɠ����悤�ɉ䖝���Ă���B
����Ȃ����������Ǝv���Ă��܂������ς��A
�����Ă��̃��X�g�����̃V�`���G�[�V�����ʂ�A���܂ꂽ�u�Ԃ���x�������Ă���l�X�ɑ��錾�t�ł�����B
���E��10%�����E�̕x��90%�������A�n�x�̊i���͑傫���B
���������������ƉƂ��������̕x�͉��S�N�ƈ����p����Ă��������B�܂萶�܂ꂽ���_�Ŋ��Ɋi�������܂�Ă���B�������̎q�����n�R�̎q���̕x����悵�A���ꂪ����ɂ��p���ꂻ�̍����c��オ���Ă���B
�u�X�J�[�t�F�C�X�v�̋r�{�̃I���o�[�E�X�g�[���͍���Љ�h�f��̑�\�i�ƌ����鑶�݂��B
�ނ��g�j�[�ɂ��̑䎌��f���������ɂ͒��ڂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
���̉f��̍���ɗ����̂�
�u�オ������ߍ��A�����Ԃ��E���v
�Ƃ������b�Z�[�W���B
���ɂ�����������Ȃ��g�j�[�ɁA�K�b�c�Ƃ������킾���������������ł��̃��b�Z�[�W������ɋ���Ɋς���̂ɓ͂��B
�Ƃ͌����Ă��������u�オ������ߍ��A�����Ԃ��E���v���߂Ƀg�j�[�̂悤�ɐl���E���K�v���Ȃ����A�R�J�C��������ăn�C�ɂȂ�K�v���Ȃ��B
�g�j�[�̂悤�ȃK�b�c���������厖�ŁA�����ƒN�̐S�̒��ɂ�����͕W����������Ă�Ƃ������Ƃ��u�X�J�[�t�F�C�X�v����w�Ԃ��Ƃ��ł���B
�s���̎����̒��A�u���C�A���E�f�E�p���}�ƃI���o�[�E�X�g�[�������グ�����̍�i�́u�h���b�O�v�u�o�C�I�����X�v�`�ʂ�����������ȉf��A����(�u�Í��X�̊���v)�ւ̖`���A�ȂǕ]�_�ƒB�Ƀ{���N�\�Ɍ���ꂽ�B
���������ۂ̋��Ǝ����͑S�Ăŏ��o��łQ�ʂɂ���q�b�g�����B
���̍\�����̂���i���畨�����]�_�ƁA�܂�́u�オ������ߍ��A���v���ϋq�̔M���������Ă��ăf�E�p���}�ƃI���o�[�E�X�g�[���̔M�ӂ��u�Ԃ��E�����v�悤�Ő��X�����B
�����Ă��̉f��͍��l���b�p�[�A�����̑O�̐���I�Ɍ����ƃM�����O�X�^���b�p�[�̊ԂŃo�C�u���I�ȑ��݂ɂȂ��Ă���B
�����ɂ͂�����l���b�p�[�B�̃h���b�O�Ƌ������郊�A���ȃT�O���C�t�����̉f��Ƌ����镔�����傫���Ƃ͎v�����A�s���̃}�C�m���e�B�̐l�X���Ȃ̃K�b�c�����ł̂�����Ă����Ƃ����g�j�[�E�����^�i�̃}�C���h�ɃG���p���[�����g����Ă��镔�����傫�����낤�B
�����̃��X�g�Ńg�j�[�͓G�̃M�����O�W�c�Ɉ͂܂�}�V���K���ŖI�̑��ɂ����B
����ł��g�j�[�͂������ԁB
�u���͂܂������Ă邼�I�I�v
�g�j�[�E�����^�i�̓K�b�c�����ł̂�������j���B
�ȒP�ɂ͓|��Ȃ��B
�s���̓�l�̒j���A�K�b�c�����߂Ă��̉f���������B
�]�_�ƒB�͂�����{���N�\�ɒ@�����B
������������ς��ϋq�B�̓g�j�[�E�����^�i����A�u���C�A���E�f�E�p���}�ƃI���o�[�E�X�g�[������A�K�b�c��������ĉf����x�������B
������40�N�߂��߂������ł����̉f��͗����Ă���B
���������̕���Ȃ��l�X�ɃK�b�c��^���A�M�����O�f��̋������Ƃ��ė��������Ă���B
�A���E�p�`�[�m�u�J���[�g�̓��v�@�u���C�A���E�f�E�p���}�߂��y�ĂȂ�ڂ�����I
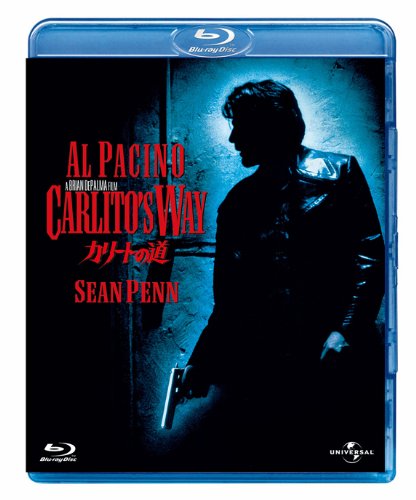 �A���E�p�`�[�m�̃M�����O�f��ƌ����A�u�S�b�h�t�@�[�U�[�v�T�[�K�A�������́u�X�J�[�t�F�C�X�v�Ƃ��܂���ˁB����́A������i�ł͂����ł����ǁA�����A���E�p�`�[�m�M�����O�f��̒��ł͉e���������������i�u�J���[�g�̓��v�ł��B�ȉ��l�^�o������S�b�h�t�@�[�U�[���D���l�I�ɂ́A�u�S�b�h�t�@�[�U�[�v���D...
�A���E�p�`�[�m�̃M�����O�f��ƌ����A�u�S�b�h�t�@�[�U�[�v�T�[�K�A�������́u�X�J�[�t�F�C�X�v�Ƃ��܂���ˁB����́A������i�ł͂����ł����ǁA�����A���E�p�`�[�m�M�����O�f��̒��ł͉e���������������i�u�J���[�g�̓��v�ł��B�ȉ��l�^�o������S�b�h�t�@�[�U�[���D���l�I�ɂ́A�u�S�b�h�t�@�[�U�[�v���D...
�u�Z���g�E�I�u�E�E�[�}���@���̍���v�̓��u�X�g�[���[�ł͂���܂���I�A���p�`�[�m...
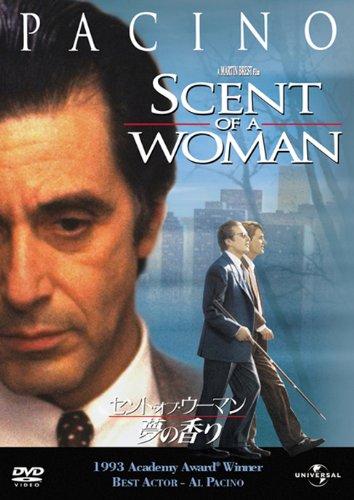 �A���E�p�`�[�m�͑�D���Ȃ�ł����A�����Ɗς��ɂ��܂����B���̍�i�B�ςĂ݂�ƁA�薼���珟��ɑz�����Ă������e�Ƃ͑S�R�Ⴄ�ł͂���܂��B����ɏ��V�̂�������̗�������C���[�W���Ă��܂����B�������A���e�͎�҂ƘV�l�̐S�̌𗬂ł����ˁB�A���E�p�`�[�m�͂��̉f��ŔO��̃A�J�f�~�[�剉�j�D�܂��l�����Ă�...
�A���E�p�`�[�m�͑�D���Ȃ�ł����A�����Ɗς��ɂ��܂����B���̍�i�B�ςĂ݂�ƁA�薼���珟��ɑz�����Ă������e�Ƃ͑S�R�Ⴄ�ł͂���܂��B����ɏ��V�̂�������̗�������C���[�W���Ă��܂����B�������A���e�͎�҂ƘV�l�̐S�̌𗬂ł����ˁB�A���E�p�`�[�m�͂��̉f��ŔO��̃A�J�f�~�[�剉�j�D�܂��l�����Ă�...
�u�A�����J���r���[�e�B�[�v�@�P�r���E�X�y�C�V�[
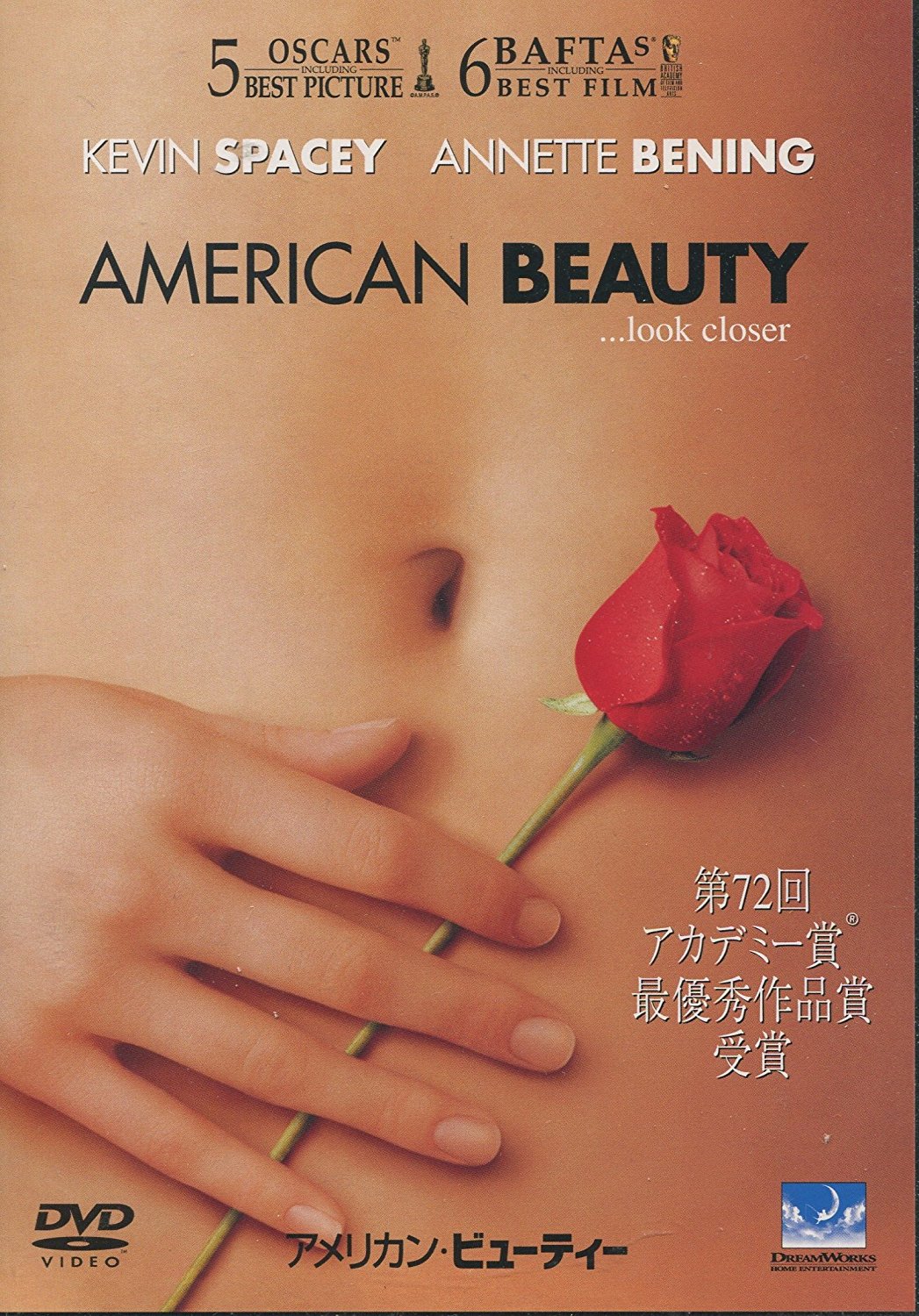 �P�r���E�X�y�C�V�[�剉�ŃA�J�f�~�[�܂��l�����u�A�����J���E�r���[�e�B�[�v�B���̉f��́A�o�����͕�����₷���ł��ˁB��l�������J�ɓo��l����������Ă���āA�e�ȉf��ł��B�Ƃ����̂��A�O���̓A���h���C�E�^���R�t�X�L�[�́u�f���\�����X�v���ς��̂ŁA����Ɣ�ׂ�ƁA���̉f��͕�����₷�����Ƃ��̏�Ȃ��̂�...
�P�r���E�X�y�C�V�[�剉�ŃA�J�f�~�[�܂��l�����u�A�����J���E�r���[�e�B�[�v�B���̉f��́A�o�����͕�����₷���ł��ˁB��l�������J�ɓo��l����������Ă���āA�e�ȉf��ł��B�Ƃ����̂��A�O���̓A���h���C�E�^���R�t�X�L�[�́u�f���\�����X�v���ς��̂ŁA����Ɣ�ׂ�ƁA���̉f��͕�����₷�����Ƃ��̏�Ȃ��̂�...
�u�L���b�`�~�[�C�t���[�L�����v�̓f�B�J�v���I�̃R�X�v���f�悾�I
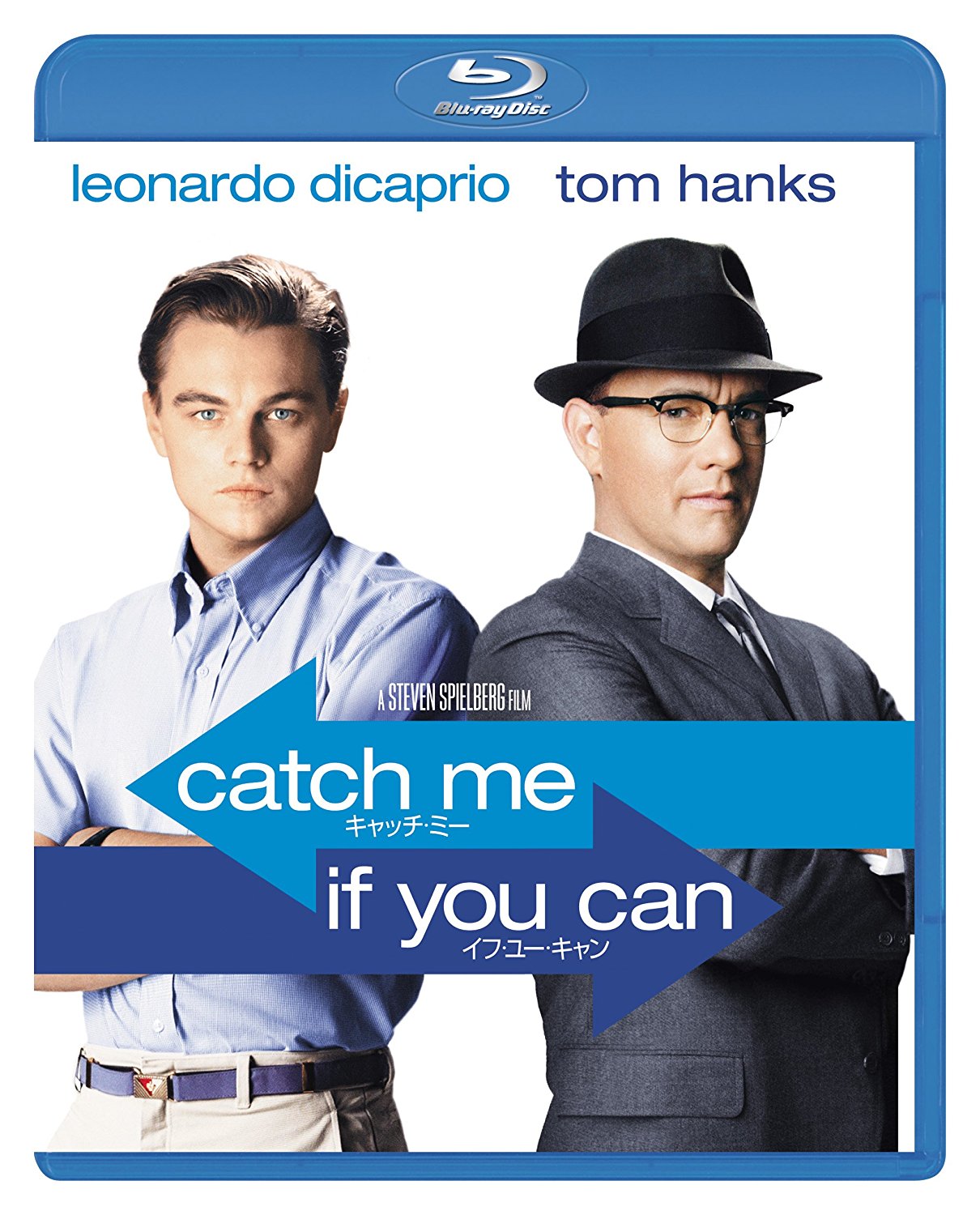 �X�s���o�[�O�~�g���E�n���N�X�̃R���r�Ƀ��I�i���h�E�f�B�J�v���I�������A���݂̍��\�t��FBI�̒ǂ�����������`�����h���}�B�u���I�̖ڂɂ́A��������D�������ȍˋC�����߂��Ă���B�ނ̃p�t�H�[�}���X�͂��̂�������������Ă���B�t�����N���������@��蔲����ꂽ�̂�80���̃p�t�H�[�}���X�ƁA������...
�X�s���o�[�O�~�g���E�n���N�X�̃R���r�Ƀ��I�i���h�E�f�B�J�v���I�������A���݂̍��\�t��FBI�̒ǂ�����������`�����h���}�B�u���I�̖ڂɂ́A��������D�������ȍˋC�����߂��Ă���B�ނ̃p�t�H�[�}���X�͂��̂�������������Ă���B�t�����N���������@��蔲����ꂽ�̂�80���̃p�t�H�[�}���X�ƁA������...
�}�C�m���e�B���|�[�g�@�g���E�N���[�Y�~�X�s���o�[�O
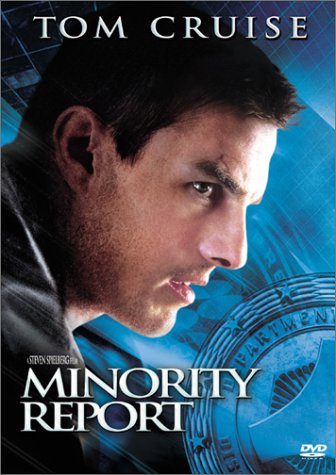 �}�C�m���e�B�E���|�[�g�@�e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@3.67�_�@�]�������@1022���E�g���E�N���[�Y�̑�\��E���E�ρA�f���A�X�g�[���[���ׂėǂ��E����̐��E�ς������ɍČ��E����������E�������̓X�s���o�[�O�f��.com�@3.5�_�@2037�l�E�ݒ肪�ʔ����E�X�g�[���[�ɖO�������Ȃ������E2...
�}�C�m���e�B�E���|�[�g�@�e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@3.67�_�@�]�������@1022���E�g���E�N���[�Y�̑�\��E���E�ρA�f���A�X�g�[���[���ׂėǂ��E����̐��E�ς������ɍČ��E����������E�������̓X�s���o�[�O�f��.com�@3.5�_�@2037�l�E�ݒ肪�ʔ����E�X�g�[���[�ɖO�������Ȃ������E2...
�u�A���^�b�`���u���v���h�f�p���}���B����������y�f��
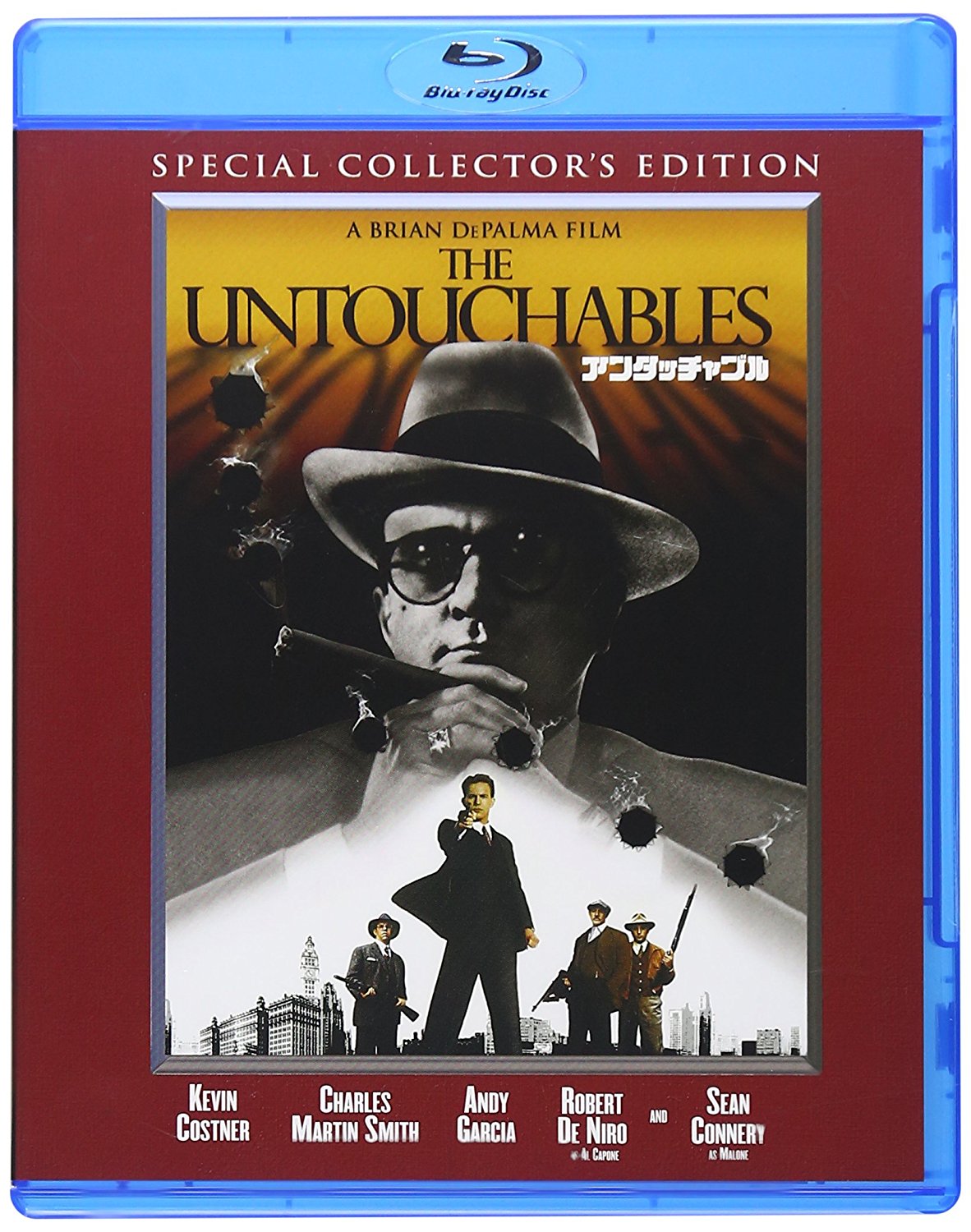 �e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@4.29�_�@�]�������@793���E�f�E�p���}�̐��`�E�f�j�[���A����ς�B�E�f�p���}�ō��E�ʔ������ǁE�o�^�������E���a�Ō�̑�O��y�f��E���ʁE�G���j�I�E�����R�[�l�E�{���ɂ��̊ḗE���ؔz��������f�p���}�f��f��.com�@3.9�_�@1095�l�E�a���j�����E�V���[...
�e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@4.29�_�@�]�������@793���E�f�E�p���}�̐��`�E�f�j�[���A����ς�B�E�f�p���}�ō��E�ʔ������ǁE�o�^�������E���a�Ō�̑�O��y�f��E���ʁE�G���j�I�E�����R�[�l�E�{���ɂ��̊ḗE���ؔz��������f�p���}�f��f��.com�@3.9�_�@1095�l�E�a���j�����E�V���[...
�A���E�p�`�[�mVS���o�[�g�E�f�E�j�[���@�u�{�[�_�[�v�@�̃I�`�͌������������c
 �e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@3.15�_�@�]�������@273���E�厖�Ȃ̂̓o�����X�Ɣz���E2�l�����������Ȃ��E�f���Ɋy���ށE�X�g�[���[���c�O�E�܂��܂��f��.com�@3.0�_�@254�l�E�f�j�[���Ƀp�`�[�m�E�����܂łЂǂ��Ȃ�āc�E�a���Y�����́E�r�{�J�X�ł��啨2�l�Ŏ��E���N�̃o���h�̍Č�����...
�e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@3.15�_�@�]�������@273���E�厖�Ȃ̂̓o�����X�Ɣz���E2�l�����������Ȃ��E�f���Ɋy���ށE�X�g�[���[���c�O�E�܂��܂��f��.com�@3.0�_�@254�l�E�f�j�[���Ƀp�`�[�m�E�����܂łЂǂ��Ȃ�āc�E�a���Y�����́E�r�{�J�X�ł��啨2�l�Ŏ��E���N�̃o���h�̍Č�����...
�����̑��z�@��o���̃V�[���͓��{�f��j�ɂ̂��閽�����J�b�g�I�~�t�l�ƗT���Y������...
 �w�����̑��z�x�@�e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@3.81�_�@�]�������@105���E�B�e�̉ߍ����͂킩�����E�U��Ԃ�j�����̃��}���E�j�̈ꐶ�̎d���Ƃ͉����E�܂��Ɉ̋ƁE���߂Ďv���A�d�C�͑�ɁB�E���{�f��̒�́E�͍�A�������ē͋�J���Ă���E���{�f��̌ւ�E�������������f��.com�@3.7�_�@...
�w�����̑��z�x�@�e�T�C�g���r���[�܂Ƃ�Yahoo!�f��@3.81�_�@�]�������@105���E�B�e�̉ߍ����͂킩�����E�U��Ԃ�j�����̃��}���E�j�̈ꐶ�̎d���Ƃ͉����E�܂��Ɉ̋ƁE���߂Ďv���A�d�C�͑�ɁB�E���{�f��̒�́E�͍�A�������ē͋�J���Ă���E���{�f��̌ւ�E�������������f��.com�@3.7�_�@...
